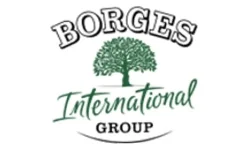日本のスマート・トランスポーテーション市場規模、シェア、動向、予測ソリューション・サービス別、輸送形態別、用途別、地域別、2026-2034年
日本のスマート・トランスポーテーション市場の規模とシェア:
日本のスマートトランスポーテーション市場規模は、2025年にUSD 7.5十億と評価されました。今後、IMARC Groupは市場が2034年までにUSD 15.3十億に達すると推定しており、2026年から2034年の期間中、年平均成長率(CAGR)は8.27%と見込まれています。この市場は、接続車両、自律システム、電動モビリティにおける技術革新の進展により成長しています。さらに、スマートシティの推進、持続可能性への取り組み、効率的で安全かつ環境に優しい交通ソリューションへの需要の高まりも、日本のスマート交通市場の展望に有利な影響を与えています。
|
レポート属性
|
主要統計
|
|---|---|
|
基準年
|
2025
|
|
予想年数
|
2026-2034
|
|
歴史的な年
|
2020-2025
|
|
2025年の市場規模
|
75億ドル |
|
2034年の市場予測
|
153億米ドル |
| 市場成長率(2026-2034) | 8.27% |
行政機関は、より広範なスマートシティ構想の一環としてスマート交通を優先し、インテリジェント交通システムの開発に多大な資源を割り当てている。高度交通管理システムの配備や自動運転車・電気自動車(EV)の普及促進などのプログラムが市場成長に寄与している。さらに、高齢者人口の増加により、高齢者や移動に不自由な人のニーズを満たすように設計されたバリアフリー・インフラや自律走行車など、アクセシブルな交通ソリューションの開発が必要となっている。さらに、自然災害の影響を受けやすいことから、緊急事態管理用に設計されたスマート交通システムの開発が促されている。リアルタイムのモニタリングや自動リルートなどの技術により、地震や台風などのイベント時の回復力が確保される。
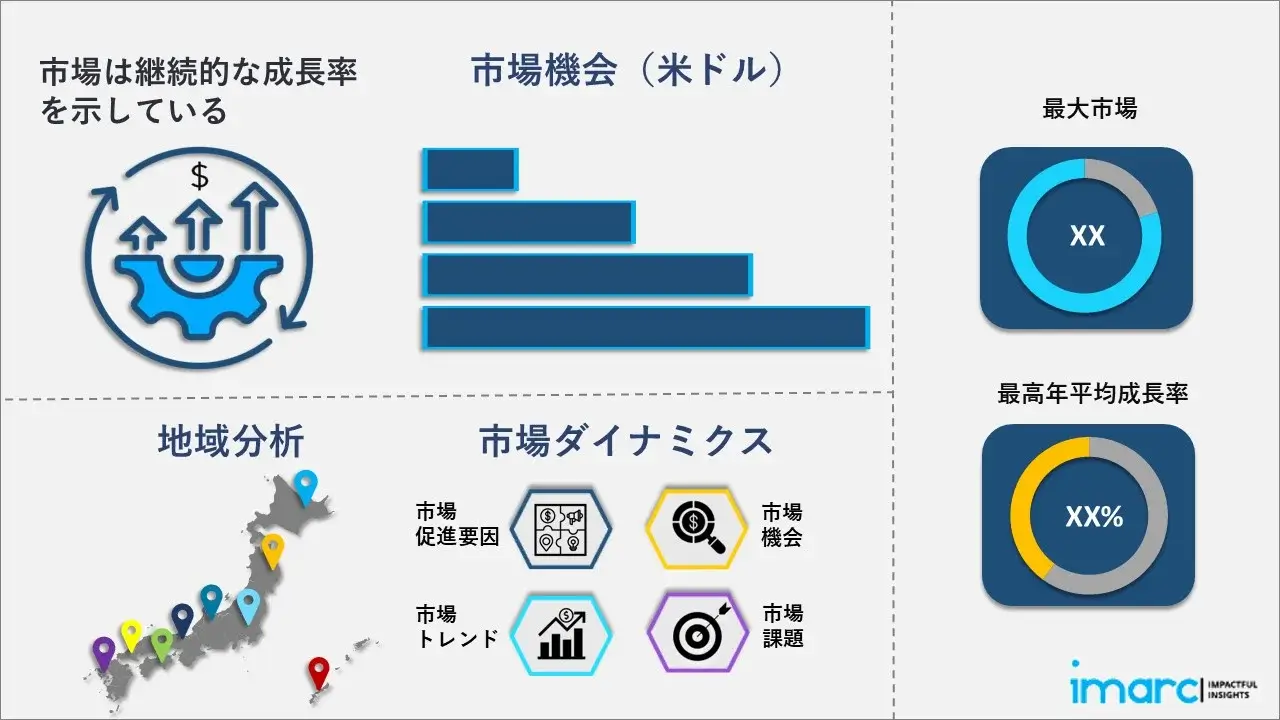
これとは別に、日本は、特に自動車と電気通信分野における技術とイノベーションに取り組む主要国の一つである。輸送における人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、5Gの統合は、スマートシステムの能力を高め、リアルタイムのデータ共有、予知保全、シームレスな複合輸送を可能にする。特に5G技術の展開は、超高速データ伝送、低遅延、信頼性の高い接続を可能にすることで、スマート輸送の機能を強化している。これは、自律走行や交通管理に不可欠なリアルタイムの車車間(V2V)や車車間(V2I)通信をサポートする。さらに、自動車会社、テクノロジー企業、インフラ・プロバイダー間のパートナーシップは、スマート交通ソリューションの展開を加速させている。こうした連携はイノベーションを促進し、自律走行システムやスマートパーキングなど多様な技術の統合を可能にする。
日本のスマート交通市場の動向:
高齢化とアクセシビリティの改善
日本の人口動態、特に高齢化は、アクセシビリティの向上を目的としたスマート交通ソリューションの導入に大きな影響を及ぼしている。国連人口基金(UNFPA)によると、2024年の日本の人口は1億2,260万人で、65歳以上の高齢者が30%近くを占める。この人口動態の変化は、高齢者や障害者に対応した交通システムの開発に拍車をかけている。自動化されたサービス・キオスク、音声作動システム、段差を低くしたり手すりの配置を改善するなどのアクセシビリティ機能を備えた車両などのイノベーションがある。さらに、これらのテクノロジーは、移動に困難がある人に合わせたリアルタイムの支援やナビゲーションを提供するユーザーフレンドリーなアプリと統合されつつある。これらの進歩は、包括性を促進するだけでなく、交通ネットワークがすべての利用者の多様なニーズを満たすことを保証し、より統合的でまとまりのある社会に貢献する。
高まる環境への懸念
気候変動とその影響に対する人々の意識が高まる中、運輸部門における温室効果ガス排出量の削減が大きく推進されている。行政機関やさまざまな地方公共団体は、この目的を達成するためにスマート交通技術を活用している。スマート交通システムは、車両の流れの効率を改善し、電気バスや自転車など環境に優しい交通手段の利用を促進することで、この目標に貢献する。リアルタイムのデータ分析を統合することで、これらのシステムはよりスマートな意思決定を促進し、交通渋滞の緩和と排出量の削減につながる。こうしたシステムの採用は、人口密度の高い都市部における重要な懸念事項である、公害の最小化とエネルギー使用の最適化に役立つ。2024年、現代自動車は日本で中型電気バス「エレック・シティ・タウン」を発売した。このバスは、最大航続距離330kmを実現する145kWhのバッテリー、先進の安全システム、双方向充電に対応していることが特徴である。現代自動車は、岩崎グループに5台を供給する契約を皮切りに、屋久島のすべてのバスとタクシーをゼロ・エミッション車に置き換えることを目指している。
自律走行車(AV)へのシフト
大手自動車メーカーやハイテク企業が自律走行車(AV)開発に多額の投資を行っていることから、日本は自律走行モビリティのリーダーとしての地位を確立しつつある。この移行は、特に地方や十分なサービスを受けていない地域で、アクセスしやすく、効率的で安全な交通手段を求める需要を生み出している高齢化によって促進されている。自動運転車は、人間のドライバーの必要性を軽減することができるため、自律走行車は労働力不足に対する解決策を提供する。さらに、行政機関は、AVの技術革新と公共交通システムへの統合を支援するための政策を導入し、資金を提供することによって、重要な役割を果たしている。2024年、日産は横浜で、センサーを搭載した電気自動車「日産リーフ」のプロトタイプを使って自動運転技術を披露した。このデモンストレーションは、地方自治体とのパートナーシップのもと、2027年までに商用自動運転タクシーを含む自律走行モビリティサービスを開始するという計画の進展を示すものであった。この構想は、日本の労働力不足に対処し、スマートモビリティ・ソリューションを推進するものである。
日本のスマート交通産業のセグメント化:
IMARCグループは、日本のスマート交通市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2026年から2034年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は、ソリューションとサービス、輸送モード、アプリケーションに基づいて分類されています。
ソリューションとサービスによる分析:
- ソリューション
- ハイブリッド発券管理システム
- 駐車場管理・誘導システム
- 統合監督システム
- 交通管理システム
- その他
- サービス
- ビジネスサービス
- プロフェッショナル・サービス
- クラウドサービス
ソリューション分野(ハイブリッド発券管理システム、駐車場管理・誘導システム、統合監視システム、交通管理システム)は、業務効率を高め、ユーザー体験を向上させ、渋滞を緩和する能力があるため、スマート交通市場において極めて重要である。これらのソリューションは、輸送ワークフローを強化し、資源利用を改善し、リアルタイム情報を提供することで、より持続可能で効率的な輸送システムの構築に大きく貢献する。
サービス・セグメント(ビジネス・サービス、プロフェッショナル・サービス、クラウド・サービス)は、戦略的、技術的、運用的サポートを提供することで、市場で極めて重要な役割を果たしている。ビジネス・サービスは企業の業務強化を支援し、プロフェッショナル・サービスはシステムの導入と維持管理に関する知識を提供し、クラウド・サービスは拡張可能なデータ処理と即時分析を促進し、よりインテリジェントな輸送ソリューションのための円滑な統合とより良い意思決定を保証する。
交通手段別の分析:
- 道路
- 鉄道
- エアウェイズ
- 海事
日本のスマート・トランスポーテーション市場は、コネクテッド・カー、スマート交通管理、自律走行技術の統合に牽引され、道路が顕著なシェアを占めている。リアルタイムの交通監視、インテリジェントな交通信号、車両対インフラ通信といった先進的なソリューションが、交通の流れを最適化し、交通安全を向上させている。さらに、EVの台頭とスマートパーキングシステムの開発がこのセグメントの成長に寄与しており、道路ベースの輸送をより効率的で持続可能なものにしている。
鉄道は、安全性、運行効率、乗客の全体的な体験を向上させるために、インテリジェント・テクノロジーを導入している。自動列車システム、予知保全、統合発券ソリューションなどの進歩は、鉄道部門に革命をもたらしている。鉄道におけるインテリジェント輸送の選択肢には、リアルタイムの列車追跡、高度な信号システム、他の輸送モードとのスムーズな統合が含まれ、貨物・旅客サービス双方の接続性とシステム全体の信頼性を高めている。
航空では、スマート輸送システムが、フライト時刻表の合理化、航空交通管制の強化、乗客の快適性の向上によって空の旅を向上させている。コネクテッド・プレーン、予知保全、ライブ気象情報などの技術は、運航効率と安全性を高めている。さらに空港では、スムーズなチェックイン、セキュリティー検査、手荷物管理のためのインテリジェント・システムの導入が進んでおり、遅延や運営経費を最小限に抑えながら、より効率的で合理的な体験を乗客に提供している。
海運部門では、物流、港湾管理、船舶運航を改善するため、スマート輸送ソリューションの導入が進んでいる。自己運航船舶、ライブ・トラッキング、予期保全などの技術は、海上輸送の有効性と安全性を高めている。インテリジェント港湾は、センサーとデータ分析を採用し、オペレーションを最適化し、混雑を最小限に抑え、貨物管理を強化している。これらの進歩は、世界的な貿易経路に沿った製品の移動を改善し、海運部門における持続可能性を促進するために特に不可欠である。
アプリケーションの洞察:
- サービスとしてのモビリティ
- 公共交通機関
- トランジット・ハブ
- コネクテッド・カー
- ビデオ管理
- その他
モビリティ・アズ・ア・サービスは、さまざまな交通手段を組み合わせ、公共交通機関、ライドシェア、レンタカー、その他のサービスを1つのプラットフォームでスムーズに利用できるようにするもので、急速に拡大している。このアプリは、効果的なルート計画、リアルタイムのモニタリング、決済の統合を促進することで、ユーザー体験を向上させることを目的としている。移動の柔軟性を向上させ、特に移動の要件が多様で入り組んでいる都市や混雑した地域では、インテリジェント交通システムの不可欠なコンポーネントとして位置づけられる。
公共交通分野は、信頼性、効率性、持続可能性を向上させるため、スマート交通技術に依存している。リアルタイムの追跡、インテリジェントな発券、まとまったスケジューリング・システムを活用することで、公共交通サービスはますます使いやすく効率的になっている。このセクションでは、優れたサービスを提供し、都市部の混雑を緩和するために、路線計画を改善し、車両管理を強化し、さまざまな交通手段間のスムーズな連携を促進することを強調する。
交通ハブは、大量の乗客と車両を管理するインテリジェント・センターへと進化している。スマートテクノロジーを取り入れることで、これらのハブは、楽な乗り換え、より良い混雑コントロール、待ち時間の短縮のために強化されている。AIを活用した分析、即時更新、自動化システムなどのテクノロジーは、運行、安全性、ユーザー体験を向上させるとともに、電車、バス、タクシーなどさまざまな交通手段間の接続性を高めている。
コネクテッドカー部門は、インフラ、他の車両、クラウドサービスと連携するための高度な通信技術を車両に装備することに注力している。これにより、ライブの交通情報、ナビゲーションのヘルプ、車の診断、事故防止などの安全機能の向上といった機能が可能になる。コネクテッド・カーはインテリジェントな交通ネットワークに不可欠であり、交通管理の強化、経路計画の改善、交通安全の全般的な向上を促進する。
ビデオ管理は、強化されたセキュリティ、監視、運用上の洞察を提供することにより、日本のスマート交通市場の成長に重要な役割を果たしている。車両、交通監視カメラ、公共交通システムにおける高度な監視技術は、乗客の安全性を高め、犯罪を抑止し、交通状況を追跡する。これらのシステムは、事故の特定、リアルタイムの交通管理、交通網の監視における意思決定の強化のためにビデオ解析を採用しており、その結果、安全性と効率性の両方が促進される。
その他、スマート・パーキング・ソリューション、EV充電ステーション、車両管理システムなど、さまざまなアプリケーションがある。これらのアプリケーションは、駐車場の最適化、効率的な車両運行、電気自動車への移行支援といった利便性を提供することで、交通エコシステム全体を支えている。
地域分析:
- 関東地方
- 関西・近畿地方
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- 東北地方
- 中国地方
- 北海道地方
- 四国地方
東京を含む関東地方は、高い人口密度と高度な技術的枠組みを背景に、スマート交通分野の重要な中心地となっている。日本の経済と技術の中心地であるこの地域では、自動運転車、インテリジェント交通制御システム、電気自動車充電ネットワークなど、最先端の交通イノベーションが広く導入されている。
大阪や京都などの都市を擁する関西・近畿地方は、発達した交通システムと新たなスマートシティプロジェクトで知られている。この地域は、公共交通機関の強化やコネクテッド・ビークル・システムの開発など、統合交通ネットワークに重点を置いている。
名古屋のような重要な産業拠点がある中部地方は、個人と製品の輸送の強化を目指している。この地域では、大規模な製造業と運輸業を強化するために、コネクテッド・ビークル、インテリジェント・ロジスティクス、自動運転技術の利用が増加している。
九州・沖縄地方は、大都市圏と地方圏の両方において、交通の効率性と持続可能性の向上を重視している。この分野における重要な進歩は、電気バスの導入、インテリジェント・モビリティ・サービス、公共交通ソリューションの統合である。自治体と企業が協力してスマート交通技術の利用可能性を向上させ、住民と観光客の双方にとって持続可能で相互接続された交通手段を育成している。
東北地方では、スマート・トランスポーテーションを通じて、地方や遠隔地におけるコネクティビティとアクセシビリティを改善することに重点が置かれている。主なプロジェクトには、自動運転車やスマート・モビリティ・ソリューションを統合し、輸送の欠陥に対処して物流を改善することなどがある。
広島などの都市がある中国地方は、スマートモビリティの革新と環境に優しい技術を活用することで、交通インフラの改善に努めている。電気自動車の充電インフラの整備、交通管理システムへのデータ分析の導入、交通問題に取り組むための自律走行車の役割の調査などに力を入れている。
特徴的な地形と厳しい気候で知られる北海道は、環境の影響に耐えうる高度でスマートな交通手段に力を注いでいる。この地域は、電気自動車、自動運転公共交通機関、天候に対応した高度な交通システムの導入を奨励している。
競争環境:
市場の主要な参加者は、技術的な機能の向上と製品のラインナップ拡大に注力しています。自動運転車技術、インテリジェントインフラストラクチャ、および電動モビリティオプションの向上を目指し、研究活動にリソースを投入しています。テック企業、自動車メーカー、地方自治体の間でのパートナーシップが、インテリジェント交通管理システム、コネクテッドビークル、モビリティ・アズ・ア・サービス(MaaS)ソリューションの進歩を促進しています。さらに、持続可能性が主要な焦点となっており、電気自動車(EV)を通じた排出削減やエコフレンドリーな交通の促進を目指した取り組みが行われています。戦略的な提携や買収により、企業は市場でのプレゼンスを向上させ、急速に変化するスマート輸送分野での影響力を拡大しています。2024年、日本航空(JAL)は、電動マイクロモビリティを通じてエコフレンドリーな移動オプションを提供するためにLimeと提携しました。この提携により、JALマイレージ会員はLimeのサービスを利用することでマイルを貯めることができ、Limeは港湾ネットワークを拡大することが可能になります。このサービスはまず沖縄で開始され、他の都市への拡大が計画されており、住民や旅行者にスムーズで環境に優しい移動手段を提供します。
本レポートでは、日本のスマート交通市場の競争環境について包括的な分析を行い、主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています。
最新ニュース:
- 2024年12月:May Mobilityは、トヨタ自動車九州の宮田工場(日本、福岡)で、トヨタのe-Paletteプラットフォームを活用した自動運転車サービスを導入しました。このサービスは、工場労働者や訪問者の効率的な輸送を提供することを目的としています。
- 2024年10月:トヨタ自動車とNTTは、交通事故のない社会の実現に向けた「モビリティAIプラットフォーム」の共同プロジェクトを発表した。このプラットフォームは、最先端のAI、通信、データ中心技術を取り入れ、個人、自動車、インフラをつなぐ。このパートナーシップには、2030年までに5,000億円の投資が提案されており、大規模な導入が予定されている。
- 2024年9月:MONET Technologiesは、東京ウォーターフロントシティにおいて自律走行モビリティサービスを2024年度後半に開始することを発表しました。このサービスでは、レベル2の自動運転技術を搭載したトヨタのシエナミニバンが使用され、有明、お台場、青海エリアで運行を開始します。利用者は「MONET」アプリを通じて乗車を予約でき、将来的にはサービスエリアの拡大と車両の追加を予定しています。
- 2024年9月:日本では2029年3月までに新幹線の自動運転が開始される予定で、東日本旅客鉄道(JR東日本)は長岡駅と新潟駅を結ぶ37マイルの区間で自動運転の機能試験を実施している。この計画は、日本の高齢化に伴う労働力不足に取り組むものである。2029年度には、新潟駅付近の未使用軌道での完全自律走行試験が予定されている。
- 2024年7月:Alvest GroupとEasyMileは、空港や産業現場向けに自律走行型牽引トラクターEZTowの展開を拡大する合弁会社TractEasyを立ち上げた。成田国際空港での日本航空のEZTowの導入は注目に値する。このベンチャーは、EasyMileのドライバーレス技術とTLDの産業分野の専門知識を組み合わせ、イノベーションと効率化を推進する。
日本のスマート・トランスポーテーション市場レポートスコープ:
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 分析基準年 | 2025 |
| 歴史的時代 | 2020-2025 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 単位 | 億米ドル |
| レポートの範囲 |
歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
|
| ソリューションとサービス |
|
| 輸送モード | 道路、鉄道、航空、海運 |
| 対象アプリケーション | モビリティ・アズ・ア・サービス、公共交通、トランジット・ハブ、コネクテッド・カー、ビデオ管理、その他 |
| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
ステークホルダーにとっての主なメリット:
- IMARC’のレポートでは、2020年から2034年にかけての日本のスマート交通市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
- この調査レポートは、日本のスマート交通市場の市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
- ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が日本のスマート交通業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
- 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。
Need more help?
- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.
- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.
- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.
- For further assistance, please connect with our analysts.
 Request Customization
Request Customization
 Speak to an Analyst
Speak to an Analyst
 Request Brochure
Request Brochure
 Inquire Before Buying
Inquire Before Buying




.webp)




.webp)