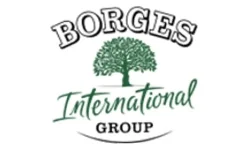日本の水素生成市場規模、シェア、動向、予測技術、システムタイプ、用途、地域別、2026-2034年
日本の水素発電市場概要 2026~2034年
日本の水素生成市場規模は、2025年にUSD 11.0十億と評価されました。今後、IMARC Groupは市場が2034年までにUSD 15.6十億に達すると推定しており、2026年から2034年の期間中、年平均成長率(CAGR)は3.90%と見込まれています。この市場は、政府の取り組みや産業・エネルギー需要の増加により急速に成長しています。さらに、グリーン水素インフラの開発が進んでいること、水素のさまざまな産業での応用が拡大していること、そして水素供給チェーンにおける国際的なパートナーシップの強化が、市場拡大を後押ししています。
|
レポート属性
|
主要統計
|
|---|---|
|
基準年
|
2025
|
|
予想年数
|
2026-2034
|
|
歴史的な年
|
2020-2025
|
|
2025年の市場規模
|
110億米ドル |
|
2034年の市場予測
|
156億ドル |
| 市場成長率 2026-2034 | 3.90% |
クリーンなエネルギー源としての水素を支援する強力な政府プログラムと規制が、日本の水素発電市場を推進する主な要因である。水素は、2050年までにカーボン・ニュートラルの達成を目指す日本政府のエネルギー転換戦略の重要な要素である。燃料電池技術やグリーン水素プロジェクトといった水素製造のためのインフラは、補助金、税制優遇措置、多額の支出を受けている。さらに、日本の水素基本戦略や水素社会ロードマップには、産業、発電、輸送などさまざまな産業で水素の利用を拡大するための詳細な計画が示されている。例えば、日本は2024年、日本水素協会とアドバンテッジパートナーズとともに、東南アジアにおける発電、液化技術、輸送施設を中心とした水素プロジェクトを支援する1,500億円規模のファンドを計画した。このような取り組みにより、水素生成技術の革新と投資を促進する環境が整いつつある。
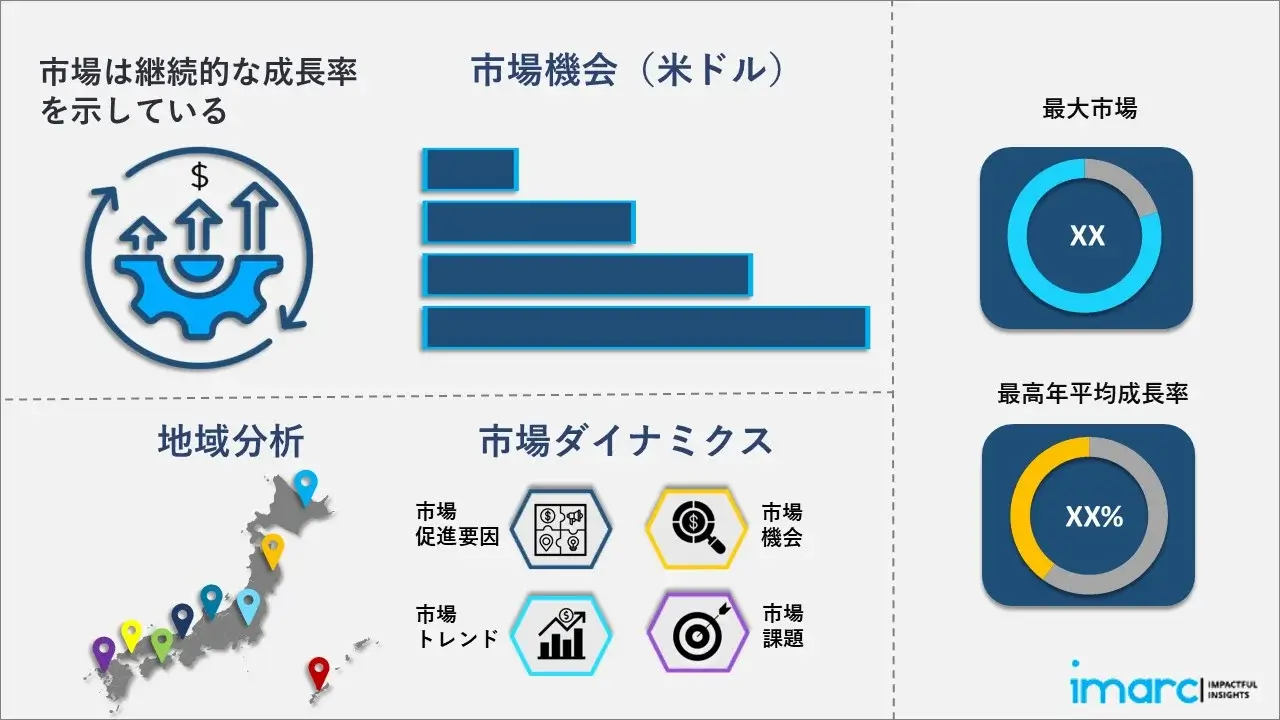
日本の産業・エネルギーセクターは、二酸化炭素排出量を削減する持続可能なソリューションとして水素に注目している。鉄鋼、化学製造、エレクトロニクスなどの産業は、厳しい環境規制を満たすため、水素ベースのプロセスを採用している。さらに、エネルギー分野では、発電や再生可能エネルギーの貯蔵媒体として水素が注目を集めている。例えば2024年、東芝は田中貴金属工業の湘南工場向けに500kWのH2Rex™ 水素燃料電池システムを受注し、よりクリーンで効率的な電力ソリューションに対する日本の産業・エネルギー需要の増大に対応した。この需要の高まりが水素発電市場を後押しし、日本は世界の水素経済におけるリーダーとしての地位を確立しつつある。
日本の水素生成市場の動向:
グリーン水素インフラの加速的な開発
日本が2050年までにカーボンニュートラルを達成するための国家戦略の主要な要素の一つは、グリーン水素インフラの整備です。そのため、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用して電解を通じて水素を生産する取り組みが段階的に拡大されます。政府の資金提供、民間投資、電解槽技術のコスト削減が、この移行を後押ししています。現在、多くの大規模なグリーン水素プロジェクトが進行中で、持続可能な水素経済を実現可能にするために生産コストを削減することを目指しています。例えば、2024年には、ENEOS、出光興産、北海道電力が、洋上風力で駆動する100 MWの電解槽を使用して地域工場や北海道製油所向けに年間10,000トンのグリーン水素供給チェーンを計画しました。このようなグリーン水素への注力は、日本が環境の持続可能性にコミットしていること、そしてクリーンエネルギーイノベーションで主導的な役割を果たすという野心を強調しています。
産業界における水素利用の拡大
現在、水素の用途は、輸送、発電、産業プロセスなど、あらゆる分野で拡大しています。日本では、水素を燃料電池車(FCV)、水素動力列車、海洋船舶に統合しており、燃料補給インフラへの投資拡大がこれを支えています。例えば、2024年には、日本の経済産業省が持続可能な航空技術を革新することを目的とした次世代水素動力旅客機の開発に向け、4兆円(約260億ドル)の官民共同イニシアチブを立ち上げました。また、電力部門では、水素がグリッド規模のエネルギー貯蔵や火力発電所のクリーン燃料として使用されています。さらに、鉄鋼および化学産業では、水素を基盤とした技術が、より厳しい排出規制への対応とともに受け入れられつつあります。このような水素の多部門への採用が日本で注目を集めており、水素生成の需要を生み出しています。
水素サプライチェーンのためのグローバル・パートナーシップの強化
日本は、優れた水素サプライチェーンの開発に向けて国際的パートナーシップに取り組んでいる。再生可能エネルギー充足国との契約関係により、低コストの水素輸入が可能になった。合弁事業は、生産規模の拡大、貯蔵・輸送技術の改良研究、確実な供給を目的としている。例えば、2024年10月、エアバス・アップネクストと東芝エネルギーシステムズは、燃料と冷却に-253℃の液体水素を利用する、水素で動く航空機用の2メガワット超電導モーターを共同開発することに合意した。こうしたパートナーシップは、日本がエネルギー安全保障を確保しつつ水素の消費需要を賄うために不可欠である。日本は、水素に支えられた経済への移行を早める機会を提供することで、世界の水素市場における役割を強化している。
日本の水素生成業界のセグメンテーション:
IMARCグループは、日本の水素生成市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2026年から2034年までの国別予測を掲載しています。市場は技術、システムタイプ、用途に基づいて分類されています。
技術別分析:
- 石炭ガス化
- スチームメタン改質
- その他
石炭ガス化とは、制御された酸素と水蒸気による高温反応によって、石炭を水素、一酸化炭素、メタンの混合ガスである合成ガスに変換する技術である。日本では、再生可能エネルギーのインフラ整備が進む中、大規模に水素を製造するための過渡的な技術として水素製造分野で利用されている。この技術は、産業用水素の安定供給を保証し、日本のエネルギー多様化目標の達成に貢献する。日本のカーボン・ニュートラルの目標に沿い、現在進行中の開発は、効率を高め、二酸化炭素排出量を削減することを目指している。
水蒸気メタン改質(SMR)は、メタンを多く含む天然ガスから、水蒸気との高温反応によって水素を取り出す技術であり、広く利用されている。SMRは、電気、運輸、産業で使用する水素を大量に製造する手頃な方法であるため、日本における水素生成事業の重要な構成要素となっている。日本は、現在SMRが水素発生を支配しているにもかかわらず、関連排出を削減するために炭素回収・貯留(CCS)技術に投資している。この戦略により、SMRは、日本がグリーン水素インフラを開発する間の応急措置として機能することができる。
システム・タイプ別分析:
- マーチャント
- キャプティブ
システム・タイプでは、商用水素は、集中施設で水素を製造し、産業、運輸、エネルギー分野を含む様々なエンドユーザーに流通・販売することを指す。マーチャント水素インフラは、安定的かつ拡張可能な供給を保証することで、日本の水素需要の増加に対応している。この技術は、パイプライン、タンカー、またはボンベによる輸送を簡素化し、大規模生産によるコスト効率を可能にする。グリーン水素インフラと現地生産能力が確立されつつある現在、マーチャント水素は供給不足を補うものであり、日本の水素経済にとって不可欠である。
システム型セグメントでは、キャプティブ水素は、外部販売用ではなく、工業施設が自家消費用に生産する水素を指す。キャプティブ水素システムは、日本の鉄鋼、化学、石油精製セクターにとって極めて重要である。この戦略により、重要な操業のための信頼できる水素源が保証されるとともに、外部供給チェーンへの依存度が低下する。日本の水素経済と環境に関する大きな目標に沿い、キャプティブ水素発電は、日本の産業界における脱炭素化のイニシアチブを支援する。
用途別分析:
- メタノール生産
- アンモニア生産
- 石油精製
- 交通
- 発電
- その他
応用分野でのメタノール製造は、水素を主要原料として、一酸化炭素または二酸化炭素との触媒反応によってメタノールを合成する。この用途は、燃料、接着剤、プラスチックに使用される汎用性の高い化学物質であるメタノールの生産に不可欠であり、日本の水素生成セクターで使用されている。メタノールはまた、クリーン燃焼燃料の代替やエネルギー貯蔵にも使用される。日本は、メタノール製造を促進することにより、水素を産業需要に利用し、エネルギー源の多様化と低炭素経済の実現に努めている。
用途分野でのアンモニア製造は、水素を中心的な投入物として利用し、ハーバー・ボッシュ・プロセスを通じて窒素と結合させる。この用途は、工業用化学品や肥料の重要な成分であるアンモニアを生産するために不可欠であり、また、日本の水素生成分野における新たな再生可能エネルギー担体でもある。低炭素燃料および水素貯蔵媒体としてのアンモニアの可能性は、持続可能なエネルギーシステムへの転換を目指す日本の取り組みを支援するものである。日本は、アンモニアの生産量を増やすことによって、産業需要とカーボンニュートラル目標を達成するために水素を利用している。
用途分野では、石油精製所が主に水素化分解と脱硫工程に水素を使用し、燃料の品質を向上させ、硫黄排出を削減している。この用途は、より環境に優しい燃料へのニーズを満たし、日本の水素生成事業における厳格な環境規制の遵守を保証する上で極めて重要である。低硫黄のガソリン、ディーゼル、ジェット燃料は、水素を使って製造することができ、日本の持続可能性と二酸化炭素削減の目標をサポートする。精製プロセスにおける水素の使用は、日本の産業およびエネルギー・インフラの更新がいかに重要であるかを強調している。
輸送は、燃料電池自動車(FCV)、水素で動く電車、その他のモビリティ・ソリューションのためのクリーン・エネルギー源として水素を利用する。水素は、日本の運輸産業の脱炭素化とカーボンニュートラル目標の達成に向けた取り組みに不可欠である。燃料電池技術の向上と燃料補給インフラの整備は、水素自動車の利用を促進する。化石燃料への依存度を下げ、エネルギー安全保障を向上させ、持続可能なモビリティを促進する水素の輸送への統合により、日本の水素生成市場は拡大している。
アプリケーション分野では、発電がクリーン・エネルギー源としての水素を活用し、燃料電池やタービンでの水素燃焼によって電気を生産する。日本における水素発電は、低炭素エネルギー・ミックスへの移行を支援し、温室効果ガスの排出削減とエネルギー安全保障という2つの問題に取り組む。太陽光や風力のような散発的な再生可能エネルギー源のバランスをとるために、水素はグリッド規模のエネルギー貯蔵のための信頼できる選択肢である。水素発電の市場は、この統合の結果として拡大しており、日本のエネルギー強靭性を強化し、積極的なカーボンニュートラル目標を支えている。
地域分析:
- 関東地方
- 関西・近畿地方
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- 東北地方
- 中国地方
- 北海道地方
- 四国地方
関東地方は、日本で最も人口が多く、経済的に重要な地域であり、水素生成市場において重要な用途が存在する場所でもあります。先進的な研究機関、産業拠点、重要なインフラを擁する関東地方は、水素技術と応用の革新を推進している。燃料電池車への燃料供給ネットワークを拡大することで、水素の普及をサポートする一方、水素を工業生産プロセスに組み込むことで、多様な産業基盤を構築することができます。また、グリーン水素とエネルギー貯蔵のパイロット・プロジェクトをリードする関東の努力は、日本の水素経済計画の主軸となるケースを強化する国の野心と一致している。
関西(近畿とも呼ばれる)は、その産業基盤と技術的専門知識を活かしてクリーンエネルギー技術を活用し、日本の水素生産市場における重要なプレーヤーとなっています。主要企業や研究機関が集まる関西は、水素の生産、貯蔵、応用において革新を積極的に推進しています。この地域の取り組みには、燃料電池システムや水素補給ステーションなど、水素を基盤としたインフラの展開が含まれ、クリーンエネルギー技術の普及を促進しています。これらの戦略的努力は、日本のカーボンニュートラル目標と一致しており、同地域は国内の水素経済および持続可能なエネルギーソリューションの発展において重要な役割を果たすことを目指しています。
中部地方は日本にとって重要な産業の中心地であり、日本の水素生成市場に貢献している。主要な自動車産業や製造業の拠点がここにあり、水素を産業プロセスや輸送システムにさらに組み込んでいる。水素燃料電池の普及率、特に自動車分野での普及率は、業界のリーダー企業との提携を通じて進んでいる。さらに中部は、グリーン水素製造を支える再生可能エネルギー・プロジェクトに投資している。これらの取り組みは、日本のカーボンニュートラル目標に沿ったものであり、日本の水素経済におけるイノベーションと成長の中心としての中部の地位をさらに確実なものにするものである。
九州・沖縄地域は、日本の水素生成市場にとって重要な地域であり、再生可能エネルギー資源と戦略的立地を有している。膨大な太陽エネルギーと風力エネルギーを有するこの地域は、持続可能なエネルギー政策イニシアチブを支援するため、グリーン水素製造を精力的に開発している。この地域は、水素輸送やエネルギー貯蔵システムなどの水素技術研究やパイロットプロジェクトの重要な拠点である。国際市場に近いこの地域は、水素の輸出機会を拡大し、世界における水素経済という日本の構想を支えている。こうした取り組みにより、九州・沖縄は日本の水素ロードマップにおいて重要な役割を果たしている。
東北地方は日本における重要な水素生成市場の一つであり、様々な風力発電や水力発電、グリーン水素を促進する再生可能エネルギー製品と連携している。この地域は、エネルギーシステムや産業プロセスへの水素の統合に焦点を当てた革新的なパイロット・プロジェクトや研究イニシアチブを開催している。再生可能エネルギーの拠点である東北は、経済の脱炭素化と持続可能なエネルギーソリューションの拡大という国家目標に合致している。東北の取り組みは、日本の水素インフラを強化し、水素をベースとしたエネルギーシステムへの転換の基礎となる。
中国地方は、その産業技術と再生可能エネルギーの潜在力によって、日本の水素生成市場を支えている。同地域は強力な製造基盤を誇り、産業界をより持続可能なものにしながら排出量を削減するため、水素を産業プロセスに組み込んでいる。もうひとつの要因は、この地域が風力や太陽光を含むさまざまな再生可能エネルギー・プロジェクトに投資しており、グリーンな水素製造を支えていることだ。さらに、戦略的な立地のため、流通やサプライチェーンのネットワークが容易である。日本のカーボンニュートラル目標に合致しており、中国地方は水素経済の発展における重要なプレーヤーに分類されるだろう。
北海道地域は、風力発電や水力発電などの豊富な再生可能エネルギーをグリーン水素に利用することで、日本の水素生成市場に貢献している。北海道は、水素貯蔵・流通技術の革新のための試験的パイロット・プロジェクトの実施地域でもある。この地域の地理的な利点は、輸出目的で北海道内で水素を大量生産することを可能にし、世界の水素経済の最前線に立つという日本の戦略にさらに関連する。北海道の貢献は、持続可能なエネルギー・イニシアチブを推進し、カーボンニュートラルという日本の目標を達成する上で極めて重要である。
四国地方は、再生可能エネルギーと産業革新で日本の水素生成市場を支えている。現在、四国の太陽光発電と風力発電の能力は非常に高く、持続可能な国家政策と目標に向けてグリーン水素製造を進めている。水素は、地域のさまざまな産業や輸送手段に組み込まれており、クリーン・エネルギー技術の統合を加速させている。四国における戦略的イニシアチブは、水素貯蔵・流通インフラをさらに強化し、日本の水素経済と低炭素エネルギーへの移行に貢献する。
競争環境:
日本の水素生成市場の競争環境は、グリーン水素プロジェクト、先進燃料電池技術、インフラ整備に多額の投資 を行っている大手企業によって支配されている。例えば、2024年9月、防衛省は三菱重工業とジャパン マリンユナイテッドに対し、それぞれ9億8,000万ドルと9億3,000万ドルでイージスシステム搭載艦2隻の建造を発注した。加えて、国際的な利害関係者との協力や、水素の製造、貯蔵、輸送のための革新的なソリューションが、市場競争力を牽引している。政府の支援は、国内およびグローバル企業の成長の可能性をさらに高めている。
本レポートでは、主要企業の詳細なプロフィールを掲載し、日本の水素生成市場における競争環境を包括的に分析している。
最新ニュース:
- 2024年11月, 三菱重工グループの一員であるMHIサーマルシステムズは、アイシン工業から新しい安城工場向けの大規模な帯水層熱エネルギー貯蔵(ATES)システムを受注しました。これは、日本の中部地域における初の実用的なATESの導入となります。
日本の水素生成市場レポートスコープ:
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 分析基準年 | 2025 |
| 歴史的時代 | 2020-2025 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 単位 | 億米ドル |
| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
|
| 対象技術 | 石炭ガス化、スチームメタン、その他 |
| 対象システムの種類 | 商人、捕虜 |
| 対象アプリケーション | メタノール製造、アンモニア製造、石油精製、輸送、発電、その他 |
| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
ステークホルダーにとっての主なメリット:
- IMARC’の調査レポートは、2020年から2034年までの日本の水素生成市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析します。
- この調査レポートは、日本の水素生成市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
- ポーターの五つの力分析は、新規参入者の影響、競争の激しさ、供給者の交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威を評価する際に利害関係者を支援します。この分析は、日本の水素生成業界における競争のレベルと市場の魅力度を把握するのに役立ちます。
- 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。
Need more help?
- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.
- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.
- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.
- For further assistance, please connect with our analysts.
 Request Customization
Request Customization
 Speak to an Analyst
Speak to an Analyst
 Request Brochure
Request Brochure
 Inquire Before Buying
Inquire Before Buying




.webp)




.webp)