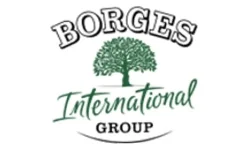日本の培養肉市場レポート ソース別(鶏肉、牛肉、魚介類、豚肉、鴨肉)、用途別(ナゲット、ハンバーガー、ミートボール、ソーセージ、ホットドッグ)、エンドユーザー別(家庭用、外食産業)、地域別 2026-2034
市場の概要:
日本の培養肉市場規模は、2025年に 16.3百万米ドル に達しました。今後、IMARC Groupは、同市場が 2034年までに70.1百万米ドル に達し、2026年~2034年の期間に年平均成長率(CAGR)17.60% で成長すると予測しています。栄養食の普及に加え、動物を飼育する必要がない、環境への影響が少ない、公衆衛生上のリスクが減少するなど、培養肉の利点に対する個人の意識が高まっていることが、主に市場成長の原動力となっている。
|
レポート属性
|
主要統計
|
|---|---|
|
基準年
|
2025 |
|
予想年数
|
2026-2034 |
|
歴史的な年
|
2020-2025
|
| 2025年の市場規模 | 16.3百万米ドル |
| 2034年の市場予測 | 70.1百万米ドル |
| 市場成長率(2026-2034) | 17.60% |
培養肉は、少量の動物細胞を使用して実験室で育てられるもので、動物を屠殺する必要を完全に排除しています。この革新的なアプローチにより、従来の畜産業が抱える問題を回避し、大腸菌(E. coli)などの汚染リスクを防ぐことができます。さらに、培養肉の生産は環境に優しく、従来の肉産業と比較して土地や水の使用量が少なく、汚染物質の排出も少なくなります。従来の肉産業は、メタン(CH4)、二酸化炭素(CO2)、亜酸化窒素(N2O)といった温室効果ガスの排出に寄与しているため、培養肉はより持続可能な選択肢として注目されています。
.webp)
日本の培養肉市場の動向:
日本の培養肉市場は、肉の生産と消費の在り方を革新する可能性を秘めていることから、大きな成長を遂げ、ますます注目を集めています。深い食文化と食品安全への強い関心を持つ日本では、培養肉の利点が広く認識されつつあり、これは市場成長を促進する重要な要因となっています。主な成長要因の一つは、培養肉の環境上の利点に対する意識の高まりです。耕作可能な土地が限られ、資源の不足が懸念される中で、日本は環境負荷の削減を目指しています。培養肉の生産は、従来の畜産業と比較して土地や水の使用量が大幅に少なく、温室効果ガス排出への影響も小さいため、日本の持続可能性目標と一致しています。さらに、培養肉生産における高度な食品安全性と品質管理は、目の肥えた日本の消費者に好意的に受け入れられており、地域市場に好影響を与えています。これに加えて、従来の肉加工に伴う汚染や疾病のリスクが排除される点も大きな魅力です。培養肉分野での研究開発が進展し、投資や政府の支援が増加する中で、予測期間中に地域市場はさらなる成長を遂げると期待されています。
日本の培養肉市場のセグメンテーション:
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2026年から2034年までの国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、供給元、用途、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。
ソース・インサイト:
- 家禽類
- 牛肉
- シーフード
- 豚肉
- 鴨
本レポートでは、ソースに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには鶏肉、牛肉、魚介類、豚肉、鴨肉が含まれる。
アプリケーションの洞察:
- ナゲッツ
- ハンバーガー
- ミートボール
- ソーセージ
- ホットドッグ
また、用途に基づく市場の詳細な分類と分析も報告書に記載されている。これには、ナゲット、ハンバーガー、ミートボール、ソーセージ、ホットドッグが含まれる。
エンドユーザーの洞察:
- 世帯
- フードサービス
本レポートでは、エンドユーザー別に市場を詳細に分類・分析している。これには家庭用サービスと食品サービスが含まれる。
地域の洞察:
- 関東地方
- 関西・近畿地方
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- 東北地方
- 中国地方
- 北海道地方
- 四国地方
また、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的に分析している。
競争環境:
この市場調査レポートは、競争環境に関する包括的な分析も提供しています。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、すべての主要企業の詳細なプロフィールが提供されています。
日本の培養肉市場レポートカバレッジ:
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 分析基準年 | 2025 |
| 歴史的時代 | 2020-2025 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 単位 | 百万米ドル |
| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
|
| 対象ソース | 鶏肉、牛肉、魚介類、豚肉、鴨肉 |
| 対象アプリケーション | ナゲット、バーガー、ミートボール、ソーセージ、ホットドッグ |
| 対象エンドユーザー | 家庭、外食 |
| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
このレポートで回答される主な質問:
- 日本の培養肉市場はこれまでどのように推移してきたのか、そして今後数年間はどのように推移していくのか?
- COVID-19が日本の培養肉市場に与えた影響は?
- 日本の培養食肉市場のソース別内訳は?
- 日本の培養肉市場の用途別内訳は?
- 日本の培養肉市場のエンドユーザー別の内訳は?
- 日本の培養肉市場のバリューチェーンにはどのような段階があるのか?
- 日本の培養食肉の主要な推進要因と課題は何か?
- 日本の培養肉市場の構造と主要プレーヤーは?
- 日本の養殖肉市場における競争の度合いは?
ステークホルダーにとっての主なメリット:
- IMARC’の業界レポートは、2020年から2034年までの日本の培養肉市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析します。
- この調査レポートは、日本の培養肉市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
- ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替品の脅威を評価する際に役立つ。関係者が日本の養殖肉業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
- 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。
Need more help?
- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.
- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.
- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.
- For further assistance, please connect with our analysts.
 Request Customization
Request Customization
 Speak to an Analyst
Speak to an Analyst
 Request Brochure
Request Brochure
 Inquire Before Buying
Inquire Before Buying




.webp)




.webp)