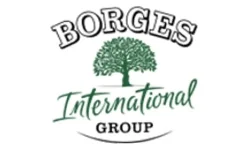日本アドベンチャーツーリズム市場レポート タイプ別(ハードアドベンチャー、ソフトアドベンチャー)、アクティビティ別(陸上アクティビティ、水上アクティビティ、エア・ベース活動)、年齢層別(30歳未満、30~41歳、42~49歳、50歳以上)、販売チャネル別(旅行代理店、ダイレクト)、地域別 2026-2034
日本のアドベンチャーツーリズム市場規模:
日本のアドベンチャーツーリズム市場規模は、2025年に 311億米ドル に達しました。今後、同市場は 2034年までに900億米ドル に達し、2026年~2034年の期間に年平均成長率(CAGR)12.54% で成長すると予測されています。市場は、国内旅行の増加、技術革新、国際旅行の増加によって牽引されています。技術的なイノベーションがアクセス性を向上させる一方、国際的な関心の高まりが、アドベンチャーツーリズム分野の成長に寄与しています。
|
レポート属性
|
主要統計
|
|---|---|
|
基準年
|
2025 |
|
予想年数
|
2026-2034 |
|
歴史的な年
|
2020-2025
|
| 2025年の市場規模 | 311億米ドル |
| 2034年の市場予測 | 900億米ドル |
| 市場成長率(2026-2034) | 12.54% |
日本のアドベンチャーツーリズム市場分析:
- 主な市場促進要因:この市場を牽引しているのは、日本の豊かな文化遺産、多様な消費者層、そして唯一無二の体験を求める冒険旅行者を惹きつける洗練されたインフラである。加えて、政府の観光イニシアティブ、アウトドア・アクティビティやウェルネス旅行の人気の高まりも市場拡大に寄与している。
- 主な市場動向:日本のアドベンチャー・ツーリズム市場のスコープによると、ハイキング、サイクリング、エコツーリズムなどのアウトドア・アクティビティの人気の高まりと、持続可能で体験的な旅行へのトレンドが市場成長に影響を与えている。さらに、人里離れた場所での体験に対する欲求の高まりが、ツアー会社をカスタマイズされたアドベンチャー・プログラムの提供に駆り立てている。
- 競争環境:日本のアドベンチャー・ツーリズム業界の大手には、Bamba Travel, Exodus Travels Limited, Intrepid Travel, INTRO Travel, Saiyu Travel Co., Ltd., The Dragon Trip, World Expeditions Travel Group, など、他にもたくさんあります。
- 課題と機会:課題としては、環境に関する複雑さ、孤立した地域における限られたインフラ、近隣地域との競合などが挙げられる。さらに、日本のアドベンチャー・ツーリズム予測によれば、ニッチ市場へのサービス提供、より没入感のある体験を提供するためのテクノロジーの活用、持続可能な開発を促進するための地域社会との協力にチャンスが見出される。
.webp)
日本のアドベンチャーツーリズム市場の動向:
国内観光客の増加
日本のアドベンチャーツーリズム市場の成長は、日本国内で冒険や独自の体験を求める日本国民の願望によって促進されています。日本観光局が発表した調査によると、国内旅行者数は推定2億7,300万人に達するとされています。これは、2023年の同等数値の97.2%、2019年の総数の93.6%に相当します。旅行者1人当たりの平均消費額は¥43,200と推定されており、2023年の消費額の100.0%、2019年の総消費額の113.4%に相当します。これらの数値は、高価格帯が年間を通じて安定することが予想されることを示しています。国内旅行での総消費額は¥11,790 billion、2023年の総消費額の97.1%を占めています。さらに、所有物よりも体験を重視する社会的動きが、沖縄でのサーフィンや日本アルプスでのトレッキングなど、多様な冒険的かつ刺激的なアクティビティへの参加を後押ししています。その結果、国内でのアドベンチャーツーリズムへの関心が地域経済に貢献するとともに、日本の観光提供を拡大し、同国の長期的な観光計画において持続可能な産業として位置付けられています。
技術の進歩
日本のアドベンチャー・ツーリズム市場の洞察によると、アドベンチャー・ツーリズム部門はテクノロジーの助けを借りて大幅な成長を遂げている。さらに、スマートフォンアプリケーション、バーチャルリアリティ体験、オンライン予約プラットフォームなどの技術の進歩により、アドベンチャーアクティビティを見つけ、参加しようとする観光客は、現在、より簡単な方法を持っている。例えば、IMARC Groupのレポートによると、日本のオンライン宿泊施設市場規模は、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.56%を示すと予想されている。この成長は、旅行者がアドベンチャー体験を計画し、スケジュールを立て、パーソナライズできるテクノロジーにより、簡単にアクセスできるようになったためと考えられる。これとともに、電動自転車や環境に優しい自動車など、交通技術の発達により、旅行者が孤立した環境的にデリケートな場所を持続的に訪問できるようになったため、冒険旅行のニーズも高まっている。
海外旅行活動の増加
日本の冒険観光市場の成長には、国際旅行活動の増加が大きく寄与しています。世界的な旅行制限が緩和され、国際的な移動がパンデミック前の水準に戻る中、日本では冒険や文化体験を求める外国人観光客の急増が見られます。例えば、2023年には、JAPAN TIMESによると、日本は2,500万人の訪問者を記録し、これは2019年以来の最高数となりました。この増加は円安に起因しており、ポストパンデミック期の観光客を引き付け、同国の経済を大きく後押ししました。また、日本政府観光局(JNTO)のデータによると、2022年の380万人から訪問者数が急増しました。さらに、12月には7カ月連続で200万人を超える国際訪問者数を記録し、最も多い訪問者数となりました。このように、観光振興へのさまざまな投資も、日本国内外での冒険観光の認知度向上に寄与しており、市場の成長を促進しています。
日本のアドベンチャー・ツーリズム市場のセグメンテーション:
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2026年から2034年までの国・地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、アクティビティ、年齢層、販売チャネルに基づいて分類しています。
タイプ別内訳:
- ハード・アドベンチャー
- ソフトアドベンチャー
本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に分類・分析している。これにはハードアドベンチャーとソフトアドベンチャーが含まれる。
ハードアドベンチャー活動は、スリルを求める人々やアドレナリン愛好家の間で人気があり、高い身体的努力、危険、そして専門知識を要することが一般的です。これには、スカイダイビングやバンジージャンプのようなエクストリームスポーツや、クライミングや急流下りといったアウトドア活動が含まれます。さらに、ハードアドベンチャー旅行者は、強烈なアドレナリンの高揚感や達成感を得られる体験を求めており、困難で過酷な環境の中で自らの限界に挑戦することのスリルや興奮に引き付けられます。これにより、日本の冒険観光市場の見通しにも変化が生じています。
ソフトアドベンチャー体験は、アドベンチャーツーリズムをよりのんびりとした親しみやすいものにしてくれるため、多くの人にとって魅力的だ。例えば、ハイキング、アニマルサファリ、カヤック、文化体験などは、発見、自然界への感謝、異文化交流を重視するソフトアドベンチャー・アクティビティである。さらに、自然界や地域社会との有意義なつながりを築くことを目指す一方で、ソフト・アドベンチャー・ツーリストは、没入型の体験、環境の持続可能性、自己啓発の機会を重視することが多い。彼らはまた、日本の変化に富んだ風景の中で思い出に残るやりがいのある冒険をすることを目的としており、日本のアドベンチャーツーリズムの需要を高めている。
活動別内訳:
- 陸上での活動
- 水上アクティビティ
- 空中活動
本レポートでは、アクティビティに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには陸上活動、水上活動、空中活動が含まれる。
陸上でのアクティビティは、スリルを求める人々や環境愛好家など、さまざまな人々を惹きつけている。これには、古い森をマウンテンバイクで走ったり、富士山の荒々しい斜面をトレッキングしたりと、日本の多様な自然環境にしっかりと根ざしたアクティビティが含まれる。ロッククライミング、キャンプ、アニマルサファリなどのアクティビティは、経験豊富な冒険家から、美しい景色の中でアドレナリンを分泌させたい初心者まで、日本の文化遺産に浸りながら楽しむことができる。
水上アクティビティは、日本の素晴らしい海岸線を探検し、水中の驚異の世界に飛び込む冒険者を魅了する。また、湘南や千葉のような有名なビーチではサーファーが理想的な波を求め、沖縄や宮古島の未開の海岸ではカヤックが人里離れた入り江や海食洞を探します。さらに、シュノーケリングやスキューバダイビングでは、多様な海洋生物や無垢なサンゴ礁で溢れる日本の色鮮やかな水中生態系を観察することができ、このエリアは静かな休暇や水中体験に最適だ。
日本の空を基盤としたアドベンチャー観光セクターは、国の美しい自然の魅力を独特の視点から楽しむ機会を提供します。奈良の古都や京都の嵐山竹林などの名所を熱気球で飛行すれば、日本の自然や文化の豊かさを空中から堪能できます。一方で、パラグライダーやスカイダイビングの冒険は、壮大な山々や広がる田園風景を背景に、アドレナリンあふれるスリルを提供し、新たな高みへと飛び立ち、日本の風景を別の角度から楽しみたいスリルを求める人々を惹きつけています。陸を探索するにせよ、海に潜るにせよ、空を翔けるにせよ、日本のアドベンチャー観光市場は、あらゆる冒険家に多様な体験を提供します。
年齢層別の内訳:
- 30歳以下
- 30–41年
- 42–49歳
- 50歳以上
本レポートでは、年齢層別に市場を詳細に分類・分析している。これには30歳未満、30-41歳、42-49歳、50歳以上が含まれる。
30歳の若者は、歴史的な竜神大橋からのバンジージャンプや沖縄でのジンベエザメとのダイビングなど、アドレナリン全開のアクティビティを日本で体験する。彼らは目新しさとスリルを求め、インスタ映えするユニークな瞬間を提供する型破りな冒険に惹かれることが多い。一方、30~41歳の層は、冒険と文化への没入の融合を求め、伝統的な旅館に泊まりながら中山道をハイキングするような体験を選ぶ。これらの旅行者は、冒険への渇望を満たしながら、日本の豊かな遺産との深いつながりを提供する体験を重視している。
42~49歳のグループは、田園風景の中をサイクリングしたり、田舎の秘湯を探検したりと、少しゆったりとした冒険を好む。彼らは興奮と静寂のバランスを求め、リラックスと若返りを促す体験を優先することが多い。さらに、50歳以上の層は、国立公園でのガイド付き自然散策や、日本の美食スポットを巡るグルメツアーなど、ゆったりとしたペースの冒険を好む。快適さ、安全性、文化的な豊かさを重視し、日本の美をゆったりと味わいながら、気の合う仲間との思い出を作るような体験を好む。
販売チャネル別内訳:
- 旅行代理店
- ダイレクト
販売チャネルに基づく市場の詳細な内訳と分析も本レポートで提供されています。これには、旅行代理店および直接販売が含まれます。
冒険家たちは、旅行代理店を通じて旅程を作成する際の利便性と専門知識を求めている。旅行代理店の知識やコネクションを頼りに、特別な体験をしたり、スムーズな旅を実現したりする。このような旅行者は、手間のかからない手配や個人的なサポートを優先し、プロがロジスティクスや予約を行う利便性を重視する。
これに加え、ダイレクト・セグメントには、冒険の計画に実践的なアプローチを好む冒険家が含まれる。これらの人々は、自主性と柔軟性を優先し、自分の好みに合わせて旅行を自由にカスタマイズすることを好む。ツアー・オペレーターやサービス・プロバイダーと直接交流することを求め、オンライン・プラットフォームや直接予約を活用して幅広い選択肢にアクセスし、仲介手数料を回避してコストを節約する可能性がある。
地域別内訳:
- 関東地方
- 関西・近畿地方
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- 東北地方
- 中国地方
- 北海道地方
- 四国地方
また、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方など、この地域の主要市場についても包括的な分析を行っている。
関東地域は東京を中心とした日本の冒険観光の活気ある拠点であり、多様なアクティビティでスリルを求める旅行者を引き付けています。東京での都市探検やハイテク体験から、富士山や日光国立公園など周辺地域でのアウトドア冒険まで、関東地域はあらゆるタイプの冒険家に何かしらの体験を提供します。そのため、主要なプレイヤーは旅行活動の増加による地域の需要を支援しています。さらに、2023年7月には、東京都品川区に本社を置く日本航空株式会社(JAL)と、東京都目黒区を拠点とするKammui株式会社が、インバウンド向けのプレミアム冒険観光市場の成長を促進するための戦略的パートナーシップを発表しました。この取り組みの主な目的は、地域社会を活性化し、地域開発の取り組みを強化することです。
京都、大阪、奈良などの都市を含む関西・近畿地方では、アドベンチャー・ツーリズムは文化的な趣を帯びている。旅行者は、古寺を探索したり、伝統的な茶道に参加したり、一日着物を着たりして、日本の豊かな歴史に浸ることができる。また、紀伊山地のハイキングやサイクリングなど、アウトドア・アドベンチャーも楽しめる。
また、中部地方は、日本アルプスの険しい山々から日本の田園地帯の穏やかな美しさまで、多様なアドベンチャー・ツーリズムの機会を誇っている。アウトドア派は立山黒部アルペンルートのようなハイキングやスノースポーツに、文化的な体験を求める人は高山のような歴史的な町を訪れたり、アートに満ちた金沢を散策したりすることができる。
これに加えて、九州・沖縄地域では、冒険観光がトロピカルな雰囲気を帯びており、沖縄の島々ではダイビング、シュノーケリング、ビーチアクティビティを楽しむ機会が提供されています。一方、九州本土では、火山地形の探索、温泉でのリラックス、そして地域特有の料理を味わうことができます。
東北地方は、荒々しい海岸線、手つかずの自然が残る森林、そびえ立つ山々など、日本のワイルドな一面を探検する冒険のチャンスです。また、北上川でのラフティングや山形の古くからの巡礼路のハイキングなど、東北は自然の美しさとアウトドアの興奮が見事に調和した場所です。
史跡や自然の驚異で知られる中国地方では、有名なしまなみ海道のサイクリング・ルートのハイキング、宮島の象徴的な厳島神社の散策、隠岐諸島の荒々しい美しさに感嘆するなど、アドベンチャー・ツーリズムを楽しむことができる。
日本最北の島、北海道は一年を通して冒険好きにはたまらない場所だ。冬は世界有数のスキーリゾート、夏はハイキングやサイクリング、広大な国立公園での野生動物ウォッチングが楽しめる。また、北海道独自のアイヌ文化は、アドベンチャー体験に豊かな文化的側面を加えてくれる。
四国地方は、のどかな雰囲気と美しい自然が魅力で、人里離れた冒険を楽しみたい人にぴったりだ。四国遍路道をハイキングしたり、秘境の温泉に浸かったり、魅力的な漁村が点在する絵のように美しい海岸線を探検したりと、都会の喧騒から逃れて穏やかな時間を過ごすことができる。
競争環境:
- この市場調査レポートは、市場の競争環境についても包括的な分析を行っています。すべての主要企業の詳細なプロフィールが提供されています。日本のアドベンチャー・ツーリズム業界の主な市場プレイヤーには、Bamba Travel, Exodus Travels Limited, Intrepid Travel, INTRO Travel, Saiyu Travel Co., Ltd., The Dragon Trip, そして World Expeditions Travel Group.
(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されている)
- 現在、市場の主要プレーヤーは、日本のアドベンチャー・ツーリズム市場のシェアを拡大するための戦略を実施している。地元のインフラに投資し、国際的な旅行代理店と提携することで、市場へのリーチを広げている。デジタル・マーケティング戦略を通じて地域の観光スポットを宣伝し、多様な嗜好に対応するオーダーメイドのアドベンチャー・パッケージを作成することに注力している。さらに、政府の観光イニシアティブとのコラボレーションは、世界的な視聴者への知名度とアクセシビリティを高めるのに役立っている。例えば、2023年9月、責任ある観光事業へのコミットメントで有名なイントレピッドトラベルは、100以上の新鮮な旅程の印象的な配列を特徴とする2024年の旅行コレクションを発表すると発表した。これらの新しい旅は、シンプルでありながら深みのある旅行体験へと意図的に軸足を移し、現地への没入と変容的な出会いに重点を置きながら、人気のあるデスティネーションを再構築することを反映している。
日本アドベンチャーツーリズム市場ニュース:
- 2023年7月: のプレミアパートナーに日本航空(JAL)が選ばれた。 アドベンチャーツーリズムの世界最大イベントとして知られる「アドベンチャートラベルワールドサミット北海道大会(ATWS2023)」。JALは、ATWS2023のスポンサーシップ契約のもと、機内誌やビデオプログラムを通じて、冒険旅行のスリルを積極的に伝え、現地ガイドの努力を紹介しました。さらに、アイヌ文化を中心とした特別ツアーを企画し、北海道と開催地域の豊かな遺産を紹介しました。JALはリーディング・パートナーとして、アドベンチャー・ツーリズム(AT)を日本の観光産業の重要な一分野として位置づけています。これは、旅行者に斬新な体験価値を提供するとともに、持続可能な開発目標(SDGs)と地域資産を観光に統合し、成長と持続可能性を促進するイニシアティブを育成するものです。
- 2024年3月: イントレピッドはファスト・カンパニー誌の「世界で最も革新的な企業」に5回連続で選ばれ、革新への継続的なコミットメントを明確にした。旅行、レジャー、ホスピタリティ部門において、イントレピッドは先駆的なカーボン・ラベル・プログラムが評価された。2023年、イントレピッドはウェブサイトの500以上の旅行ページにカーボンラベルを導入し、旅行者1人あたりが1日に排出するCO2総量に関する貴重な情報を提供した。このイニシアチブは、旅行の選択が環境に与える影響について旅行者が理解できるようにするためのもので、イントレピッドの持続可能性と責任ある観光への取り組みを反映している。今回の認定により、イントレピッドはグーグル、マテル、マタドール・ネットワークといった業界大手と並ぶ名誉ある企業となった。
- 2024年5月: 京都に本社を置くツアーオペレーター、オク・ジャパンは、持続可能で文化的に豊かな旅行を専門としている。同社は、ガイド付きおよびセルフガイドのウォーキングツアーに参加する旅行者と、同社がサービスを提供する地域社会とのサポートに同等の重点を置いている。同社は、ビジネス・オーナーが英語を話す人々とより自信を持って交流できるようにすることを目的とした、さまざまなコミュニティ・セッションを組み込んだ。これらのセッションは、参加者が一般的なフレーズに慣れることや、文化の違いや規範を効果的にナビゲートするための文化的ニュアンスの理解といったトピックをカバーしている。
日本のアドベンチャーツーリズム市場レポートスコープ:
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 分析基準年 | 2025 |
| 歴史的時代 | 2020-2025 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 単位 | 億米ドル |
| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
|
| 対象タイプ | ハードな冒険、ソフトな冒険 |
| 対象活動 | 陸上アクティビティ、水上アクティビティ、空中アクティビティ |
| 対象となる年齢層 | 30歳未満、30–41歳、42–49歳、50歳以上 |
| 対象販売チャンネル | 旅行代理店, ダイレクト |
| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
| 対象企業 | Bamba Travel, Exodus Travels Limited, Intrepid Travel, INTRO Travel, Saiyu Travel Co., Ltd., The Dragon Trip, World Expeditions Travel Group, など。 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
このレポートで回答される主な質問:
- 日本のアドベンチャー・ツーリズム市場はこれまでどのように推移してきたのか、そして今後どのように推移していくのか?
- COVID-19が日本のアドベンチャーツーリズム市場に与えた影響とは?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場のタイプ別内訳は?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場のアクティビティ別の内訳は?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場の年齢層別の内訳は?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場の販売チャネル別の内訳は?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場における主要な推進要因と課題は何か?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場の構造と主要プレーヤーは?
- 日本のアドベンチャーツーリズム市場における競争の度合いは?
ステークホルダーにとっての主なメリット:
- IMARC’の産業レポートは、2020年から2034年までの日本のアドベンチャーツーリズム市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析します。
- この調査レポートは、日本のアドベンチャーツーリズム市場の市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
- ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が日本のアドベンチャーツーリズム業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
- 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。
Need more help?
- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.
- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.
- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.
- For further assistance, please connect with our analysts.
 Request Customization
Request Customization
 Speak to an Analyst
Speak to an Analyst
 Request Brochure
Request Brochure
 Inquire Before Buying
Inquire Before Buying




.webp)




.webp)